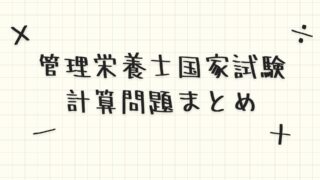 特集
特集
管理栄養士国家試験 計算問題解説まとめ
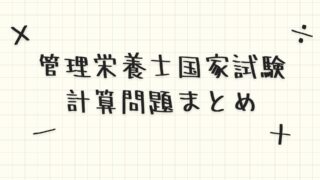 特集
特集  特集
特集 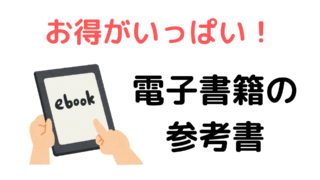 書籍紹介
書籍紹介 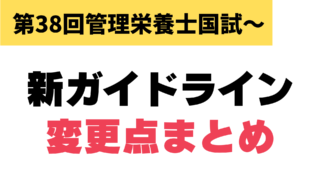 特集
特集 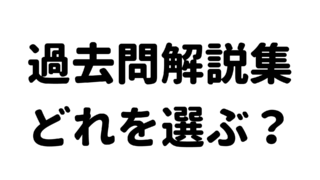 書籍紹介
書籍紹介 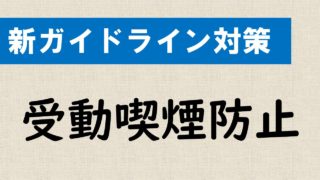 特集
特集 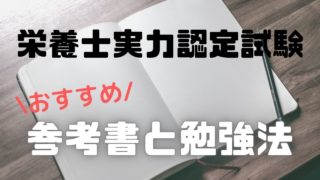 書籍紹介
書籍紹介 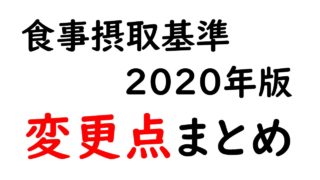 特集
特集  特集
特集 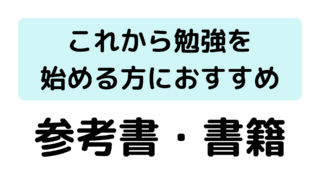 書籍紹介
書籍紹介  特集
特集 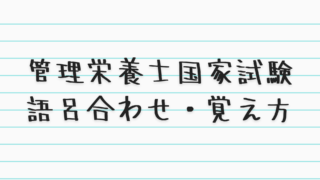 特集
特集 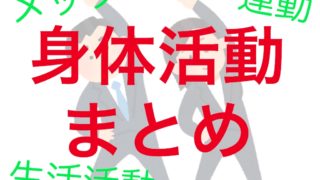 特集
特集  特集
特集  書籍紹介
書籍紹介  特集
特集 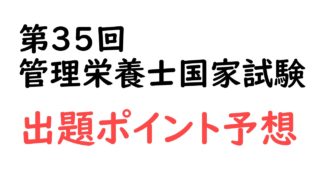 特集
特集 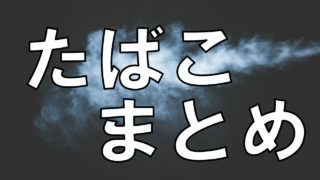 特集
特集  応用栄養学
応用栄養学  応用栄養学
応用栄養学  応用栄養学
応用栄養学  応用栄養学
応用栄養学  応用栄養学
応用栄養学  応用栄養学
応用栄養学  応用栄養学
応用栄養学  応用栄養学
応用栄養学  応用栄養学
応用栄養学  応用栄養学
応用栄養学