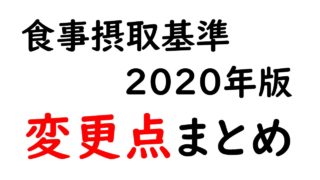 特集
特集
日本人の食事摂取基準(2020年版) 変更点まとめ
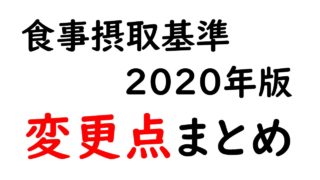 特集
特集 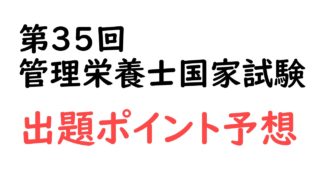 特集
特集  特集
特集 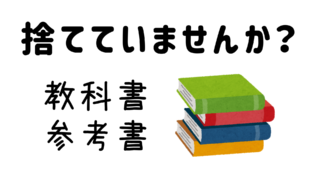 特集
特集 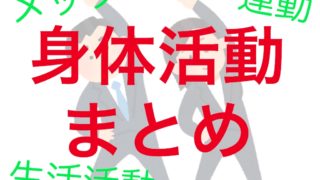 特集
特集 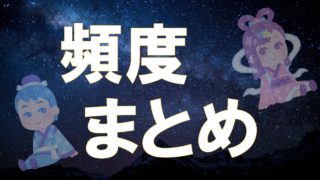 特集
特集 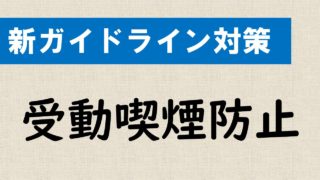 特集
特集  特集
特集  特集
特集 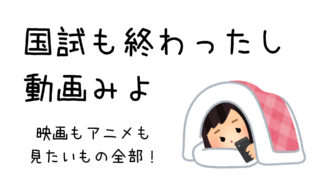 特集
特集  特集
特集  特集
特集 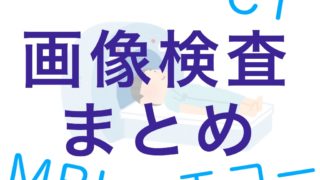 書籍紹介
書籍紹介  特集
特集 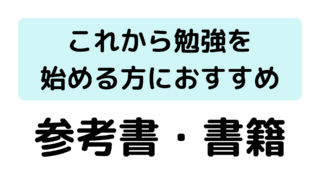 書籍紹介
書籍紹介 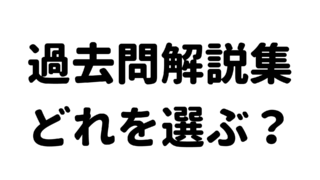 書籍紹介
書籍紹介 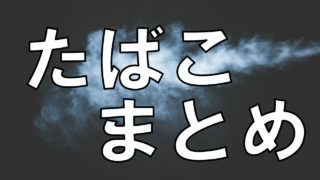 特集
特集 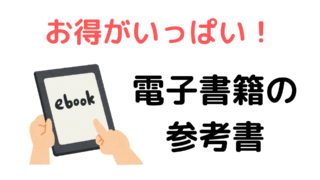 書籍紹介
書籍紹介  栄養教育論
栄養教育論  栄養教育論
栄養教育論  栄養教育論
栄養教育論  栄養教育論
栄養教育論  栄養教育論
栄養教育論  栄養教育論
栄養教育論  栄養教育論
栄養教育論  栄養教育論
栄養教育論  栄養教育論
栄養教育論  栄養教育論
栄養教育論