 特集
特集
【一覧】経口血糖降下薬 作用まとめ
 特集
特集 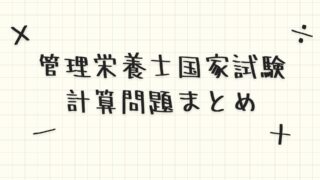 特集
特集 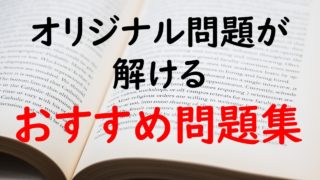 書籍紹介
書籍紹介 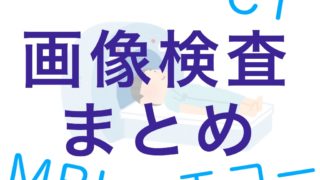 書籍紹介
書籍紹介 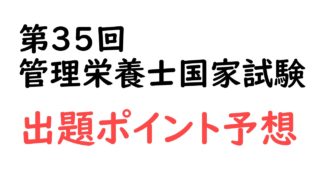 特集
特集 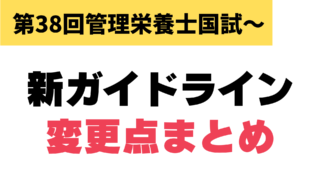 特集
特集 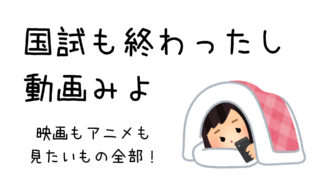 特集
特集 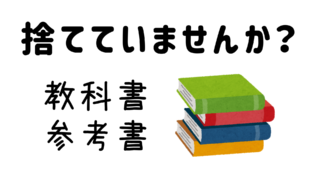 特集
特集 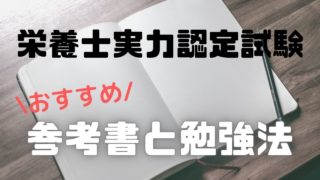 書籍紹介
書籍紹介  書籍紹介
書籍紹介  特集
特集 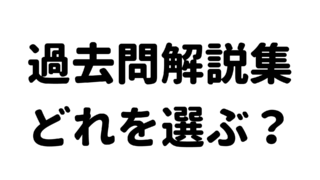 書籍紹介
書籍紹介 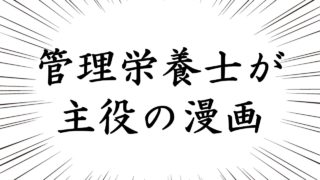 書籍紹介
書籍紹介  特集
特集 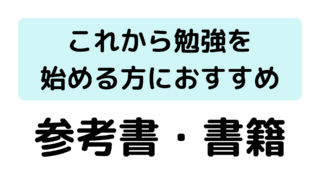 書籍紹介
書籍紹介  特集
特集  特集
特集 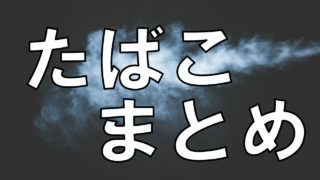 特集
特集  臨床栄養学
臨床栄養学  臨床栄養学
臨床栄養学  人体の構造と機能
人体の構造と機能  人体の構造と機能
人体の構造と機能  臨床栄養学
臨床栄養学  臨床栄養学
臨床栄養学  臨床栄養学
臨床栄養学  臨床栄養学
臨床栄養学  臨床栄養学
臨床栄養学  給食経営管理論
給食経営管理論